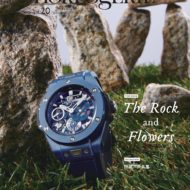かつての銀時計は、現代のプラチナ時計である。

(Photo by Adam Jaime on Unsplash)
いまわたしの目の前に、カメラマン・立木義浩巨匠が最晩年の柴田錬三郎先生を仔細に撮影して私家版の印画紙をそのまま綴じた写真集がある。これは有名なブックデザイナーの江島任先生が渾身の力を込めてデザインしたこの世に3冊しか存在しない稀覯本の写真集なのである。 わたしはこの写真集を仕事場のデスクの傍らに置いていつも眺めている。そのなかの1ページに柴田先生が直木賞を受賞したとき、いただいた正賞の和光の懐中銀時計がある。
「第二十六回 直木三十五賞 昭和二十七年三月 日本文學振興會 贈 柴田錬三郎君」 と、その裏蓋には刻まれている。 柴田先生自身の話によれば、直木賞は受賞したものの、原稿の注文はさっぱりだったそうだ。柴田錬三郎が世に出るきっかけを作ったのは、それから4年後の1956年であった。新潮社の「週刊新潮」に「眠狂四郎」の連載が開始されるまで待たなければならなかったのだ。ニヒルとダンディズムを融合させた剣豪の主人公、眠狂四郎は大衆に受けに受けた。
賞の話題性や評価が今日とは違って、直木賞も芥川賞も受賞したからといって、その受賞した作家に原稿依頼は殺到しなかったのであろう。そもそも芥川賞や直木賞の正賞の懐中銀時計はどうして生まれたのか。それは明治維新から第2次世界大戦がわが国の敗北で終わるまで続いた授与制度があった。帝国大学、学習院、商船学校、陸軍士官学校、陸軍騎兵学校等の学校において、各学部の首席や次席に対し、天皇からの褒章として銀の懐中時計が授与されたことに由来する。
とくに東京帝国大学では1897年から1918年までその授与制度が続き、323人が対象になった。いわゆる世に言う”銀時計組”といわれたエリートたちである。それは成績優秀に加えて人格も評価された。夏目漱石の『虞美人草』のなかの登場人物の一人の小野は、銀時計を授与された秀才という設定になっている。 その伝統が芥川賞と直木賞を設立されたとき引き継がれたのである。芥川賞と直木賞を設立したころの物書きは、貧しい若者が多かったので、発案者の菊池寛が賞金とは別に高く質に入れられるように、銀製の懐中時計を正賞にして、賞金を副賞にしたという逸話が残っている。
しかし、賞金を正賞とせず、懐中時計を正賞としたところが、菊池寛の志の高さであった。ペンや原稿用紙は商売道具であるが、時計は文士にとっての数少ない勲章となったのである。 正賞の懐中銀時計は、戦前はメーカーがまちまちで、その都度見繕っていたため、ロンジンだったりオメガだったりセイコーだったりした。また戦争がはじまる直前には、銀時計が払底して、陶芸家の河井寛次郎の壺などの記念品が銀時計の代わりに渡されたこともあった。現在は、和光の謹製のもので、時計にはWAKOとあるが、中身はセイコー製である。
銀時計は勲章・名誉という意味合いで象徴的に用いているが、菊池寛にいわせれば、それは志の高さというだろう。その点からいうと、懐中銀時計を作っていたセイコーにはその志があった。かつて外国製の腕時計が席巻する中で、国産を代表する腕時計として「Grand Seiko」で世界に打って出たのである。 しかしそれは銀時計ではなく、プラチナ時計だった。 このブランドは1960年に誕生した。初代モデルは80ミクロンの14Kの金貼り仕様であったが、ごく少量だけ製造されたプラチナモデルが存在したという。
経済白書によってもはや戦後ではないと宣言され、高度経済成長で生活も豊かになってきた時代である。そうした時代を機敏に察したセイコーが銀時計ならぬ、プレミア感のあるプラチナ製を発表したのは意義深い。ケース、美錠、裏蓋すべてがプラチナ999で作られている。そして今年独立ブランドとして羽ばたくことを決意したグランドセイコーから、世界に誇る精密な技術を満載にした初代グランドセイコー リミテッドコレクション2017<復刻デザイン>が発売された。
今回もプラチナモデルは用意されている。初代モデルの時と同様に高い志で、強い決意が必要な時にプラチナ時計が必要であったのだろう。そして特別限定のプラチナ製は、腕時計ながら懐中銀時計への憧憬を呼び起こすには十分な風格を持つ。 結論から申すと、和光の懐中銀時計とグランドセイコーの復刻モデルは、懐中時計と腕時計の違いはあるが、脈々と流れる時計のDNAは同根なのである。つまり現代の銀時計というのは、グランドセイコーのプラチナ製の時計なのであると断言出来るのだ。
残念ながらプラチナモデルは入手が困難であるが、シルバーカラーのSSモデルも発売されているので、ぜひ手に取ってみてほしい。懐中銀時計やプラチナモデルに宿された志を感じることができるだろう。
<PROFILE>
島地勝彦
Katsuhiko Shimaji [ エッセイスト&バーマン ]
「週刊プレイボーイ」(集英社)の編集長として同誌を100万部雑誌に育て上げる。その後「PLAYBOY」編集長、「Bart」創刊編集長などを務める。柴田錬三郎、今東光、開高健、瀬戸内寂聴、塩野七生をはじめとする錚々たる作家たちと仕事を重ねてきた編集者。シガーとシングルモルトをこよなく愛する。『甘い生活』、『知る悲しみ やっぱり男は死ぬまでロマンティックな愚か者』など著書多数。 週末は伊勢丹新宿メンズ館8Fのサロン・ド・シマジにて、バーカウンターに立つ。